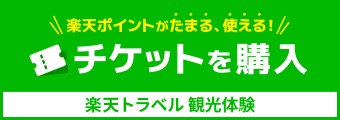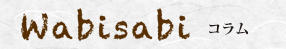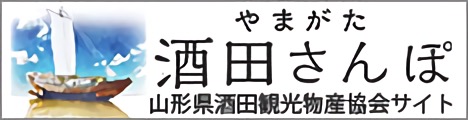Homma Museum of Art芸術・自然・歴史の融合/公益財団法人 本間美術館
コラム
若き激情の画家 小野幸吉 #4
学芸員:阿部 誠司
酒田を代表する表現者、画家・小野幸吉。
20歳10ヶ月で夭折するまでに約50点の作品を描きました。
そのどれもが今もまだ生々しく、観る者の心を激しく揺さぶります。
開催中の企画展「若き激情の画家 小野幸吉」では40点の作品を展示しています。
このコラムは、展示作品を紹介しながら小野幸吉についてお話する第4回目です。
停車場を描く
昭和4年(1929) 幸吉はしばらく酒田で制作するつもりで駅前に長屋を借り、絵画研究室を始めました。
郷里に帰っても実家で制作することを好まなかった事が要因のようですが、
実際、研究室に集まる者もおらず、常に独りで絵を描いていたようです。
まだ雪の残る3月初、小野は駅前で停車場を描いていました。
幸吉の周りには黒山の人だかりができ、
60号のキャンバスに勢いよく筆でドシドシと描く様子に、皆驚いていました。
幸吉は「おい君達!俺の絵を見て解るのか、解るまい!」と独り言のように怒鳴っていたと言います。
群集は、絵を見るよりも小野の奇怪な仕草や表情を眺め、笑ったり噂話をしていました。
この青年が二科展に入選し、新しい時代を担う才能と評されることを、
この時は誰も想像だにしなかったでしょう。
静物画
20歳で夭折した幸吉にとって、昭和4年(1929)は最晩年に当たる訳ですが、
風景画多かった以前に比べ、静物画や自画像が多くなることに気付きます。
作家が表現を確立していく中で、描く対象が変化していく事はよくありますが、
幸吉の場合は、身体の不調や死期を予感したような心情が関係しているように思われます。
 ≪ランプのある静物(C)≫ 昭和4年(1929)20歳 個人蔵
≪ランプのある静物(C)≫ 昭和4年(1929)20歳 個人蔵
特に好んで描いていたという「ランプのある静物」。
現在は3点が確認されており、そのどれもが力と心の入った幸吉の代表作となっています。
重く不安定な空間に、赤く輝き異様な存在感を放つランプは、
幸吉の存在そのものと重なって見えてくるようです。
ランプが肉体ならば、命の炎はどうでしょう?
ランプはまだまだ燃え上がり、光り輝きたい衝動や意思を感じますが、
その中身は冷たく生気を失いそうにも見えます。
次第に弱っていく自分と向き合いながらも、
まだまだ絵を描きたい、画家として光輝きたいという強い想いが、静物画からも伝わるようです。
鼻血と赤色
幸吉は病のため、よくひどい鼻血を出していました。
親交のあった人々は皆、回想の中で鼻血の話をしています。
幸吉の自画像(スケッチを含む)には、鼻が潰されていたり、鼻から下が破かれているものがあります。
真っ赤なガウンが印象的な≪ガウンを着た自画像≫も、鼻が塗り潰されています。
絶えず鼻血に悩まされていたことを思うと、
心の中に鼻血や自らの鼻について常にコンプレックスがあったのではないかと推測されます。
それは人と比べてどうこうではなく、
これさえなければもっと絵が描ける、生きられるという感情だったでしょう。
15歳で自らの墓の絵を描き、まるで死と競争しているかのような猛烈な制作の日々を送った小野幸吉。
最も好んだ色「赤」は、死を告げる血の色であり、今生きているという生の象徴だったのかもしれません。
絶筆
昭和4年(1929)11月末、幸吉は病気療養のため訪れていた温海温泉から、
一週間ほどで逃げ出すように上京します。
東京へ戻る前に、酒田の友人を訪ねました。
駅まで見送った友人に小野は「もう大丈夫だ、しっかりやるんだ」と言い、
次の展覧会の話などもしていましたが、その姿はいつになく弱々しかったと言います。
それが最後の帰省になり、最後の上京となりました。
翌12月末には病状が悪化し、危篤状態となります。
この最後の上京、一か月もない期間に描き上げたのが、
60号の大作≪ランプのある静物(A)≫です。
 ≪ランプのある静物(A)≫ 昭和4年(1929)20歳 個人蔵
≪ランプのある静物(A)≫ 昭和4年(1929)20歳 個人蔵
自らを投影するようなランプの姿を、渾身の力を込めて描いています。
ランプからは特徴的な赤い発光がなくなり、ランプ自身の力強さは薄れているようですが、
輪郭に少しだけ入る鮮烈な赤が、幸吉の情熱を表しているようです。
テーブルを俯瞰するような構図は、何かこれまでより一歩引いた、外側から己を見つめるような視線も感じます。
また、ランプやテーブルを囲む空間が、今までにない位に暖かく柔らかい色彩をしているのも印象的です。
幸吉は、弱る身体に沸きあがる激情を抱え、どんな想いでこの作品を描いたのでしょうか。
病院で
昭和4年(1929)12月、≪ランプのある静物(A)≫を描き上げてまもなく、
病状は悪化し23時間も鼻からの出血が止まらないようになり、言葉も発することが出来なくなりました。
帝国大学附属病院耳鼻科に入院したのは11日、12日とも言われています。
入院してからは回復傾向にあり、その主因となる心臓の治療に移る日を待っていました。
幸吉は、内科の治療を受ければすぐに善くなると喜びました。
病室のベッドには、筆談の紙に詩が書かれており、氷袋を下げる自分と看護婦を描いた絵が1枚ありました。
病室で書いた詩(12月23日)
夜になると電燈の月が出る
ひるは まどから
まどの雲にのって動きたい
毎日 カンゴフは白い着物だ
ベッドの中に消え入りそうだ
詩を書くと腹空けばいい
頭が半分しびれて口がきけなくなった何の為か
大先生は入道みたいだ
青い風呂敷かぶると 電燈は月みたい
回復の兆しが見えたようでしたが、12月25日に危篤状態となります。
昭和5年(1930)1月8日午後0時30分、
幸吉は母の手に食事をとりながら、腎血兼脳血栓という病名のもと20歳10ヶ月で息を引き取りました。
つづく…
2017.02.05
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 6月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
最新記事
- 2021.06.22復古やまと絵派の絵師・冷泉為恭 愛蔵の仏画
- 2021.05.11米沢藩の名君・上杉鷹山から本間家へ贈られた屏風
- 2021.02.05郷土の画人・菅原白龍 ー日本的な南画の確立に努めた画家ー
- 2021.01.24郷土の画人・市原円潭の羅漢図
- 2020.10.29鶴舞園の「月見石」
- 2020.10.21伊達政宗と千利休、2人の初めての対面を示す手紙
- 2020.07.18夏の絵画の代表、瀧を描いた作品
- 2020.07.11初夏・梅雨の時季に飾りたい絵画
- 2020.06.18唐物・高麗物・和物
- 2020.04.21鶴舞園と清遠閣を描いた作品